目次
- 1.はじめに
- 1-1.風営法店舗における消防法の重要性とは?
- 1-2.消防法に違反するとどうなる?影響とリスク
- 2.開業時に押さえるべき消防法のポイント
- 2-1.建物・内装に関する基準
- 2-2.消防設備設置の義務
- 2-3.必要な届出と手続き
- 3.開業後に必要な消防法への対応
- 4.風営法と消防法の関係を整理!
- 4-1.消防法が風営法店舗に特に関係する理由
- 4-2.こんな場合は要注意!風営法と消防法が矛盾するケースも
- 5.まとめ|風営法店舗の経営者は消防法も理解しよう
1.はじめに
飲食店やナイトビジネスを開業する際、風営法の遵守はもちろんのこと、消防法への理解と対応も欠かせません。特に、キャバクラやホストクラブ、ガールズバーなどの風営法に関する店舗では、消防法の規制が厳しく適用されることがあります。
この記事では、風営法店舗の経営者が消防法をどのように理解し、対応していくべきかについて詳しく解説します。
1-1.風営法店舗における消防法の重要性とは?
風営法で規制される店舗は、多くの場合、不特定多数の人々が利用します。そのため、火災などの災害が発生した際のリスクが高く、消防法の遵守が特に重要です。
加えて、消防法は過去の火災事故を受けて規制が強化されてきた背景を持ち、飲食店やナイトビジネスを営む店舗では、消防法への理解と適切な対応が求められます。
1-2.消防法に違反するとどうなる?影響とリスク
消防法に違反した場合、店舗の営業に深刻な影響を及ぼす可能性があります。具体的には、以下のようなリスクが挙げられます。
・営業停止命令や罰金などの行政処分
・火災発生時における損害賠償責任や刑事責任
・地域によっては、消防法違反が風営法の許可に影響を及ぼす(例:群馬県など)
これらのリスクを回避するためには、開業前からしっかりと消防法を遵守し、適切な手続きを行う必要があります。
2.開業時に押さえるべき消防法のポイント
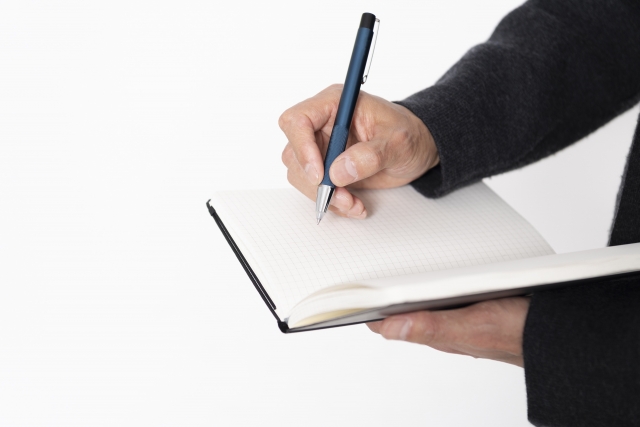
まずは、風営法店舗の経営者が開業前に知っておくべき消防法のポイントを解説します。
2-1.建物・内装に関する基準
消防法では、火災のリスクを最小限に抑えるため、特定の建物や施設を「防火対象物」として規制しています。建物の用途や構造に応じて必要な基準が設定されており、風俗営業に関する店舗(飲食店、キャバクラやホストクラブ、性風俗店など)は特定防火対象物に分類されます。
さらに、防火対象物の中でも「防炎防火対象物」に該当する場合、カーテンやカーペットは防炎性能を持つものでなければ使用できません。これらの要件を満たしていない場合、消防法違反となり罰則が科される可能性があります。
2-2.消防設備設置の義務
店舗の用途や規模によって、以下のような消防設備の設置が義務付けられています。
・消火設備:消火器やスプリンクラーの設置。
・警報設備:火災報知器や非常ベルの設置。
・避難設備:避難誘導灯や非常口の確保。
また、地階や3階以上に店舗がある場合や「無窓階」(消防法規則で定める避難上有効な開口部を有していない階)に該当する場合は、より厳格な設備の設置が求められます。
特に、小規模な飲食店であっても、調理目的で火を使用する場合には消火器の設置が必須となり、消防署の立入検査が実施される可能性があります。
2-3.必要な届出と手続き
飲食店を開業させる際には、消防法に基づいた都道府県の定めに応じ、消防署への各種届出が必要です。主な届出として、以下のものが挙げられます。
防火対象物工事等計画届
開業にともない内装工事などを行う場合は、工事開始7日前までに届出が必要です。
防火対象物使用開始届
建物の使用開始7日前までに届出が必要です。建物図面や消防用設備のリストなども添付します。
火を使用する設備等の設置届
厨房設備や給湯湯沸設備など、火災につながる恐れのある設備を設置する場合は届出が必要です。
防火管理者選任届
収容人員が30人を超える場合は、防火管理者を選任し、消防署に届け出ることが義務付けられています。防火管理者を取得するためには、1~2日の「防火管理講習」を修了する必要があります。
消防計画
防火管理者を選任する場合と同様に、従業員が30人を超える場合に届出が求められます。防火管理者が作成と管理を行い、消防設備の点検や日常的な火災予防対策などについて記載します。
消防用設備設置届
消防設備を設置した際には、設置後4日以内に届出が必要です。
風俗営業の許可申請を同時期に進める場合、消防法関連の手続きがおろそかになるケースも少なくありません。経営者自身がしっかりと理解を深めることも大切ですが、行政書士などのサポートを受けながら手続きを進めれば、よりスムーズな開業が実現するでしょう。
2-4.消防署との連携と事前確認の重要性
店舗の開業前には、管轄の消防署との連携が不可欠です。まずは事前相談に行き、各手続きが遅滞なく進むよう、必要な作業や提出書類を早めに把握しましょう。
消防署との良好な関係を築き、指導やアドバイスを積極的に受ければ、法令遵守はもちろん、火災予防体制の強化にもつながります。
3.開業後に必要な消防法への対応

ここからは、店舗の営業がスタートした後から必要になる消防法への対応を解説します。
<3-1.定期点検と報告義務
消防法では、特定の条件を満たす店舗に対して、有資格者による防火対象物点検とその報告が義務付けられています。キャバクラやガールズバーなどを含む飲食店の場合、以下の条件に該当する場合に点検対象となります。
・収容人員が300人以上の建物
・収容人員が30人以上300人未満で、地階または3階以上に店舗がある。
・店舗の階段が1つしかない(ただし、屋外に非常階段があれば免除)。
点検は年に一度実施し、その結果を消防署に報告する必要があります。また、点検および報告を怠った場合、罰則が科されることがあるため注意が必要です。
3-2.日常的な防火管理業務
店舗の防火管理者は、主に以下の業務を行う義務があります。
・避難訓練の実施:従業員を対象に、定期的な避難訓練を実施します。
・消防設備の点検:消火器や避難誘導灯などの状態を定期的に確認します。
・火気使用・取扱の監督:火気使用の安全管理と指導、火災につながる危険物の管理を行います。
・避難経路や防火設備の維持管理:火災発生時に人々が安全に避難できるよう避難経路の確保や防火戸等の点検を行います。
・収容人員の管理:収容人員の増減に応じた適切な防火管理を実施します。
これらの業務を怠ると、万が一の火災発生時に重大な責任を負うことになるため、徹底した管理が求められます。
4.風営法と消防法の関係を整理!
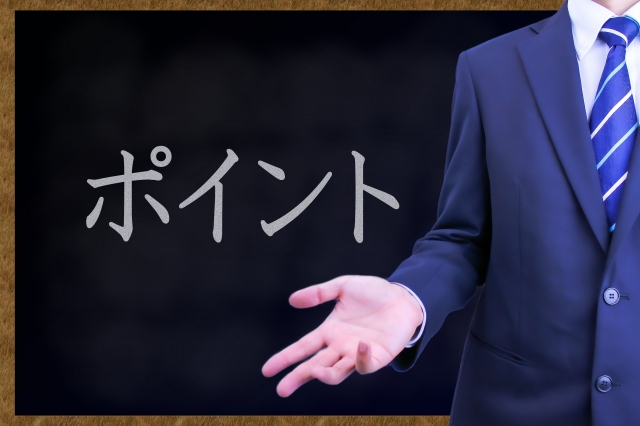
ここからは、風営法と消防法の関係を改めて整理するとともに、双方が矛盾するケースなどを紹介します。
4-1.消防法が風営法店舗に特に関係する理由
消防法は、災害時の被害を最小限に抑えることを目的としています。一方、風営法は、地域社会の良好な秩序を維持することが目的です。これらの法律は目的が異なるものの、店舗の安全性を確保するという点で密接に関係しています。
特に、キャバクラやホストクラブなどの風営法店舗では、消防法違反が風営法の許可に影響を及ぼす可能性があるため、双方の法律を理解し、適切に対応することが重要です。
4-2.こんな場合は要注意!風営法と消防法が矛盾するケースも
風営法と消防法が矛盾するケースとして、特に多いのが「防火扉の二重施錠」と「窓の封鎖」に関する問題です。
例えば、店舗出入口のドアと防火扉を兼ねるケースがありますが、防火扉の内側に内ドアを付けて施錠設備を付けてしまうと、風営法では防火扉と内扉の二重施錠となってNGとなります。
また、窓を封鎖するケースも問題です。消防法では窓が救出口として必要であるため塞ぐことは禁じられますが、一方の風営法では店外から客室内が見えてはいけないという規定があります。店舗の雰囲気を高めるために閉鎖的なデザインにするケースも多々あるため、消防法の指摘を受けやすいという訳です。
自治体によっては消防法違反がある状態では風営法の許可が下りない地域もあるため、まずは消防法に重きを置いて、風営法を遵守する必要があるでしょう。このような場合は、専門家や消防署に相談しながら適切な対応を取ることが重要です。
5.まとめ|風営法店舗の経営者は消防法も理解しよう

風俗営業店を成功させるためには、風営法と消防法の両方を遵守することが不可欠です。消防法への対応を怠ると、営業停止や罰則の対象となるだけでなく、従業員やお客様の安全を脅かすことにもなりかねません。開業前から消防署との連携を密接にし、必要な手続きや設備の設置を適切に行いましょう。
渋谷区恵比寿を拠点に活動する行政書士法人ARUTOでは、ナイトビジネスに特化した専門的なサポートを提供しています。消防法や風営法に関する手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。安心して営業を開始するために、私たちが全力でサポートいたします。




